自社に合うのはどれ?機密文書廃棄の6つの方法と選び方

機密文書は、企業にとって非常に重要な情報が含まれている文書なので、決して外部に漏洩させてはいけません。従って、利用の際の管理はもちろんのこと、廃棄にまで細心の注意を払う必要があります。そこで今回は、機密文書の廃棄方法やメリット・デメリット、選び方のポイントなどについて解説します。
会社の機密文書・書類の処分方法
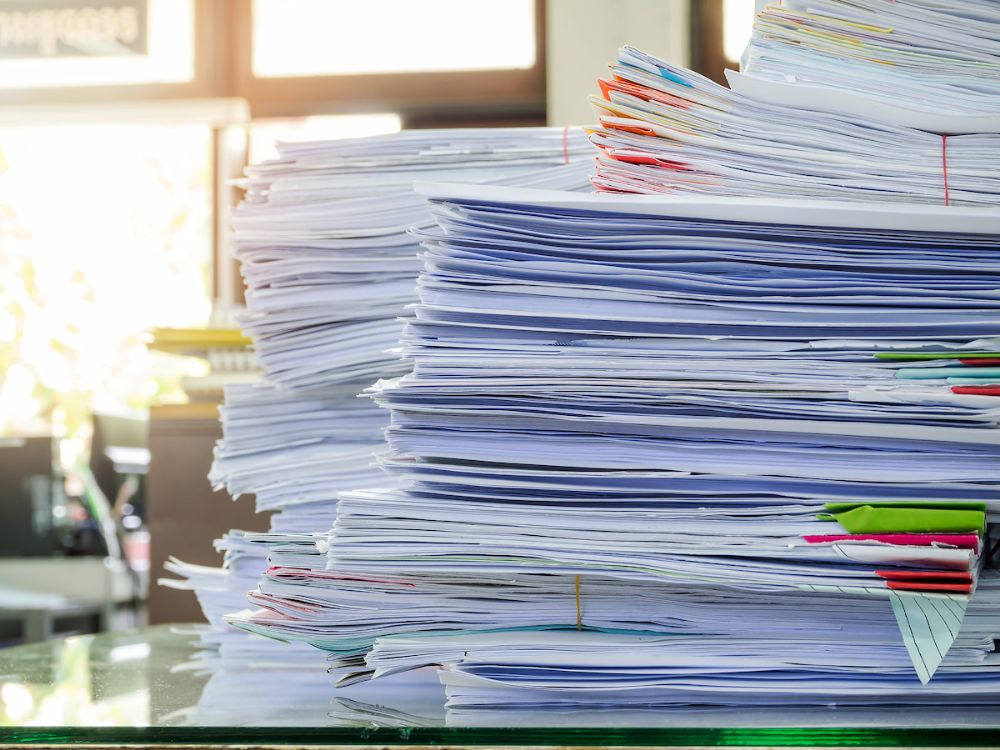
会社の機密文書や書類の廃棄方法としては、自社や自組織で実施する方法と、業者に依頼する方法のどちらかを選択することになります。
以下で、それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
自社・自組織で実施する方法
自社や自組織で行う機密文書の廃棄は、一般的な廃棄方法として知られています。
以下で、シュレッダーを用いた方法や焼却処分などの具体的な方法を解説します。
オフィスシュレッダー
自社や自組織で行われる処分の中でも、オフィスシュレッダーの利用は最も一般的な廃棄方法です。 機密文書を直接工場に持ち込み、焼却処分によって廃棄する方法です。 機密文書を直接工場に持ち込み、溶解を行う廃棄方法です。 業者に依頼して、機密文書を廃棄してもらうという方法もあります。 専門業者が大型シュレッダーを運んで企業に出張し、目の前で機密文書の断裁を行う方法です。 企業側が工場に機密文書を持ち込み、大型シュレッダーで裁断する方法です。 業者が機密文書を引き取り、工場で裁断する方法です。 社員が自らシュレッダーを使用し、機密文書を廃棄します。 目の前で機密情報の廃棄が行われるので、セキュリティ面で安心できます。。 シュレッダーの設置費や維持費、人件費など様々なコストがかかります。 パルパーと呼ばれる溶解窯の中で、水と紙を攪拌して繊維をほぐすことで、修復不能にして廃棄します。 大量の書類を一括処分することができ、書類に付属しているクリップやホチキスもまとめて処分することができます。 工場に機密文書を運搬するため、運搬中の事故や書類の散乱などのリスクがあります。 機密文書には様々な種類があり、重要度によって分類されています。 極秘文書は、機密文書の中でも最も重要度が高く、慎重な管理が要求される機密文書です。 秘文書は、極秘文書と比較すると重要度は低いですが、漏洩してはいけない情報が多く含まれています。 社外秘文書や部外秘文書は、社内での閲覧のみが許可されており、外部への漏洩が禁止されている文書です。 情報漏洩や紛失などのリスクがどの程度あるかを確認します。 自社で行う場合にかかるコストは、主に人件費です。 企業のサステナビリティ活動として、再生可能な機密文書の廃棄方法を選択することも視野に入れておくと良いでしょう。 回収時の機密文書の状態を確認し、その状態でも廃棄が可能な業者かどうかを確認しておきましょう。 機密文書以外にも廃棄してもらいたい物がある場合は、利用を検討している業者が書類以外の廃棄に対応しているかどうかを確認しましょう。 機密文書の廃棄方法を自社と外部委託のどちらにすべきかは、会社の状況を踏まえた選択になるでしょう。 外部委託に不安を感じる方へ、今回はセキュリティ・所要時間・リサイクル・効率面の課題の全てが解決できる日本パープルのサービスをご紹介します。 「保護くん」がさらに便利になったサービスです。回収ボックスの中身の量を検知し、自動で交換依頼を行ってくれます。回収ボックスの中身が満杯で利用できない、中身がはみ出てしまうといった心配がなく、安全に使うことができます。担当者は、回収ボックスの状態を常に気にする必要がなく、また交換依頼をする手間もかかりません。テレワーク中の企業にも最適なサービスです。 機密文書の廃棄方法について紹介しましたが、それぞれメリット・デメリットを踏まえて自社に合った選択をすることが重要です。なるべく早く廃棄を行いたいなら目の前で処理できる出張サービスを、安全性を優先するならISO27001認証や証明書を発行している業者を選ぶとよいでしょう。
廃棄の対象となっている機密文書を、社員自らシュレッダーにかけて廃棄します。社内に設置されているシュレッダーを利用するため、廃棄したいタイミングで廃棄を行うことができます。
一度に多くの書類を処分することができるので、機密文書が大量にある場合でも安心です。直接溶解
溶解は、リサイクルにおける工程の1つです。溶解機で水と書類を混ぜて攪拌し、粉砕して液状化することで、復元不能にします。書類の他に、付属しているクリップやホチキスなども溶解することができます。業者に依頼する方法
以下で、出張断裁や持ち込み断裁など具体的な方法について解説します。出張裁断
目の前で廃棄を行うので、セキュリティ面で安心できます。また、業者側が出向いてくれることにより、自社側の配送による書類の紛失リスクを回避することができます。持ち込み裁断
自社側で配送を行うためコスト削減が可能ですが、配送中の事故や紛失などのリスクもあるため注意が必要です。引き取り裁断
自社側は書類を業者に引き渡すだけなので、時間と労力を削減することができます。シュレッダーと溶解処理の違い

シュレッダーと溶解処理のメリットとデメリットについて、以下で詳しく解説します。シュレッダー
シュレッダーのメリットとデメリットについて、それぞれ見ていきましょう。メリット
廃棄が行われたことを確認することができるので、廃棄のし忘れなどの不安がありません。デメリット
また、シュレッダーを用いた廃棄には時間と手間がかかるため、書類が多い場合には不向きと言えます。さらに、断裁された紙片はリサイクルには向いていないため、環境への負荷が大きいです。溶解処理
溶解処理のメリットとデメリットについて、それぞれ見ていきましょう。メリット
二酸化炭素を排出しないので環境に優しく、処理後はリサイクルすることが可能です。デメリット
依頼してからすぐに廃棄されるとは限らず、廃棄は業者側のタイミングで行われるので、依頼から廃棄までに多少の時間がかかります。廃棄時に要注意な会社内に存在する機密文書(機密書類)
廃棄時に注意が必要な機密文書を、以下で3種類紹介します。極秘文書
具体的には、企業の財務に関する情報、設計図など新商品に関する情報、顧客に関する情報などです。外部に漏洩すると会社にとって非常に大きな損失となるため、社内でも限られた社員しか閲覧することができません。
廃棄のタイミングが来るまで、鍵付きの保管庫やキャビネットなどで厳重に保管しましょう。秘文書
具体的には、人事評価に関する情報、コストに関する情報、各種契約書などがあります。当該業務に携わっている社員のみが閲覧可能で、社内全体で共有することはできません。社外秘文書・部外秘文書
具体的には、業務マニュアルや議事録、統計資料などがあります。他の2つよりも相対的に重要度が低くなるだけなので、重要な文書であることに変わりはありません。機密文書の廃棄方法を選ぶ際のポイント

機密文書の廃棄には、自社で行う方法と外部へ委託する方法があります。
それぞれ選ぶ際のポイントを以下で解説するので、参考にしてみてください。セキュリティ
機密文書の中には個人情報が含まれますが、個人情報の保護に関する法律では、企業に対して委託先への管理責任が求められています。自社で廃棄する時と同じように、外部へ委託する場合も適切に処理されているか確認しなければなりません。
業者のセキュリティ対策を見極めるには、ISO27001認証(情報セキュリティ)の保有有無も一つの判断材料となります。加えて、書類廃棄処理が一社完結型であるかどうかも重要なポイントです。受付・回収・廃棄を別々の業者が委託で請け負っていることも多く、その場合は管理が行き届かないなどトラブルの原因になりかねません。一社で最初から最後まで対応してくれるサービスの方が、管理が楽で安心安全であると言えるでしょう。コストパフォーマンスのバランス
業者に依頼する場合は単位・金額が異なるので、事前に複数社で比較検討しましょう。あまりに安価でサービスが提供されている場合、セキュリティが不十分なこともあるため、コストとセキュリティとのバランスを見極める必要があります。また文書の梱包や配送などに、どれだけ手間がかかるかもチェックポイントです。再生可能かどうか
後ほどご紹介する溶解処理では、廃棄文書を再生紙などへリサイクルしている業者がほとんどです。回収時の状態
たとえば、機密文書の中にプラスチックのファイルが含まれている場合は、プラスチックも同時に廃棄可能な業者を選択する必要があります。また、少量であれば金属が含まれていても廃棄可能としている業者もあります。書類以外の廃棄の対応
対応可能な業者であれば、PCやタブレット、スマホなどの機器をまとめて廃棄してくれます。また、CDやDVDなどの電子記録媒体の廃棄が可能な業者もあります。機密文書の廃棄処理は自社でやるべき?それとも外部に委託すべき?
コスト、セキュリティ、スピードなど、会社によって重視するポイントが異なります。廃棄する文書の内容によっても、選択は変わるでしょう。しかし、機密文書の廃棄はシュレッダーでは安全とは言えません。焼却や溶解で完全に読めなくなるまで処理しなければ、悪用される可能性も大いにあり得ます。企業を守るためにも、セキュリティが充実したサービスを選ぶことが重要です。安心して任せられるおすすめの廃棄サービス
セキュリティ対策万全の機密処理サービス「保護(まもる)くん」

オフィスに鍵付き機密回収ボックス「保護(まもる)くん」を設置し、そこへ廃棄文書を投入するだけで、書類が人目や人手に触れることなく破砕処理される仕組みになっています。
おすすめポイントは、なんといってもセキュリティ対策の手厚さです。一度回収ボックスに入れると、社内の人間でも取り出すことはできません。さらに研修を受けたスタッフが、回収から廃棄まで一社完結で行います。これまでに約12,000の事業所への導入を誇る実績も、安心安全の証です。なお、日本パープルは全事業所でISO27000認証を取得しています。自動で交換依頼をしてくれる「Smart保護くん」
セキュリティやコストのバランスを見極めて自社に合った廃棄方法を
コスト削減を重視するなら自社が良いと考える方も多いと思いますが、手間や人件費を考慮すると、外部委託の方がコストパフォーマンスが良い場合もあります。今回ご紹介したサービスなどを上手に利用して、適切な文書廃棄を行いましょう。





















