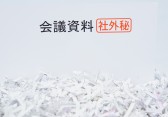機密情報が入ったUSB・CD・DVDの廃棄・処分方法は?

近年のデジタル化により、企業や個人が扱うデータはパソコンだけでなく、USBメモリやCD、DVDなどの外部媒体にも保存される機会が増えています。ところが、これらの媒体から機密情報が漏洩する事故は依然として後を絶ちません。セキュリティ対策の重要性は年々高まっているものの、「USBやCD、DVDを安全に処分する方法が分からない」という声も少なくありません。特に、パソコン本体のデータ消去には注意を払っていても、小型の記録媒体は処理が後回しになりがちです。
本記事では、USB、CD、DVDなど機密情報が入った媒体を安全かつ確実に廃棄・処分する方法について解説いたします。
機密情報漏洩のリスクは計り知れないほど大きい
まず大前提として、パソコン本体はもちろん、USBメモリやCD、DVDなどの記録媒体においても、情報漏洩事故を起こしてしまった場合のリスクは非常に大きいということを、しっかり意識しておくことが大切です。ひとたび漏洩が発生すれば、顧客や取引先への賠償金、事故後の対策費用などの金銭的負担に加え、企業としての社会的信用を大きく失うことになります。
信用を一度失えば、多くの費用と時間をかけても、元の評価や信頼を取り戻すのは難しいものです。たった一件の漏洩が経営危機や事業存続の危険につながることも珍しくありません。だからこそ、機密情報は使用時から廃棄・処分に至るまで、物理的・デジタル的な両面で徹底した安全管理が求められるのです。
USBの廃棄・処分方法

USBメモリは小型で手軽にデータを持ち運べる反面、紛失や情報漏洩のリスクが高い媒体です。パソコン本体ほど目立たないため、廃棄時の管理がおろそかになりがちですが、内部には重要な個人情報や機密データが残っている可能性があります。廃棄や処分の際には、データ消去を確実に行い、適切な方法を選ぶことが重要です。
ここでは、代表的な4つの処分方法とその注意点を解説します。
不燃ごみとして捨てる
一部の自治体では、USBメモリを不燃ごみとして処分できます。ただし、この方法はデータを消去したうえで行うことが前提です。単に削除やリセットをするだけではデータが復元されてしまう可能性があるため、上書き処理付きのフォーマットという方法での初期化や専用のデータ消去ソフト、あるいは物理的破壊(基板を割る、メモリチップを砕くなど)を行ってから捨てることが重要です。自治体によって分別ルールが異なるため、必ず事前に確認しましょう。
小型家電リサイクルボックスに入れる
全国の市区町村役場や公共施設、スーパー、家電量販店などに設置されている「小型家電リサイクルボックス」にUSBメモリを投函して処分する方法です。小型家電リサイクル法に基づき、金属やプラスチックを資源として再利用できます。ただし、こちらも投入前に必ずデータを完全消去または物理破壊しておく必要があります。
家電量販店でリサイクル回収してもらう
多くの家電量販店では、USBメモリやSDカードなどの小型記録媒体を回収するサービスを提供しています。店舗によっては無料で引き取ってくれる場合もありますが、条件や受付方法が異なるため、事前に公式サイトや店舗で確認すると安心です。持ち込みの際は、やはりデータ消去を忘れずに行いましょう。
専門業者に依頼する
最も安全なのは、USBメモリのデータ消去や物理破壊を専門とする業者に依頼する方法です。専用機器を使った物理破壊や、復元不可能なデータ消去(上書き消去、磁気破壊など)に対応しているため、機密情報の漏洩リスクを大幅に減らせます。法人向けには、大量回収や廃棄証明書の発行サービスもあり、コンプライアンス対策としても安心です。特に企業や団体での大量廃棄の場合は、この方法を検討すると良いでしょう。
業者への依頼方法は、主に3つのパターンがあります。
- ・店頭回収…業者の窓口や店舗まで直接持ち込む方法
- ・宅配回収…USBを梱包して業者へ郵送する方法
- ・出張回収…業者に指定の場所(会社や自宅)まで取りに来てもらう方法
どの方法でも、業者選びの際は「信頼できる実績の有無」「廃棄証明書の発行可否」「料金体系の明確さ」を事前に確認することが大切です。
CD・DVDの廃棄・処分方法

普通のCD・DVDであれば、ハサミで細かく割ったり、深い傷を入れたりするなど物理的に破損してから「可燃ごみ」「不燃ごみ」として捨てるのが一般的な廃棄方法です。CD・DVDはそれ自体に深い傷を入れると読み込みができない仕組みになっているため、USBのような複雑な処理は必要ありません。ただし、自治体によって分別ルールが異なる場合がありますので、必ず事前に確認してから廃棄しましょう。
自分で破壊するだけでは心配な場合や、特に音楽や映像だけでなく、個人情報や契約書、写真、映像などの重要な情報が保存されていて確実に安全に処分したい場合は、専門業者に依頼する方法もあります。業者はディスクを粉砕・熱変形・溶解などで完全に読み取り不能にし、安全に廃棄してくれます。また、なかにはCD・DVDを回収してリサイクルしている、環境に配慮した業者もあります。
法人の場合は、処分後に廃棄証明書を発行してもらえる業者を選ぶと、社内外への証明にもなります。
業者への依頼方法はUSB編と同様で、
- ・店頭回収…業者の窓口や店舗に直接持ち込む
- ・宅配回収…梱包して郵送する
- ・出張回収…業者に指定の場所まで取りに来てもらう
という3つの方法があります。
USB・CD・DVCを廃棄・処分する際の注意点

USBやCD・DVDを廃棄・処分する際は、情報漏洩を防ぐためのいくつかのポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、処分前に確認しておきたい注意点を整理します。
必要なデータは移行しておく
廃棄する前に、必要なデータは別の記憶媒体やクラウドなど安全な場所に移しておきましょう。移行し忘れると、後から復旧できず業務や生活に支障が出ることがあります。USBやCD・DVDに保存されているデータは、廃棄後には基本的に取り戻せませんので、慎重に確認しておくことが重要です。
メディア内のデータは完全に消去する
一般的なデータの消去方法は画面上で消去操作するだけですが、これだけだと表示領域で見えない部分にまだデータが残っているため、不十分な状態です。USBの場合は、専用のソフトを使った完全消去や物理破壊によって、復元できない状態にします。CD・DVDの場合は、ディスクに深い傷を入れたり粉砕して読み取り不能にするのが基本です。表面の擦り傷だけでは、データが復元される可能性があります。
自分で処理する方法、専門業者に依頼する方法、いずれの方法を選択するにしても、メディア内のデータを完全に消去して、データが読み取れない状態になっていることを確認する必要があります。これを怠ると、情報漏洩の可能性が大きくなってしまいます。
USBのデータを完全に消去する方法
USBメモリには重要な情報が残っている場合があるため、廃棄や譲渡の前にはデータが復元できない状態にすることが大切です。
ここでは、一般的に行われる3つの方法を紹介します。
パソコン上で初期化または書き換えをする
USBメモリをパソコンに接続して、上書き処理付きのフォーマットという方法での初期化や専用ソフトを使ったデータの上書き処理(書き換え)を行う方法です。単に削除やリセットをするだけではデータが復元されてしまう可能性があるため、物理的破壊(基板を割る、メモリチップを砕くなど)と併用することが推奨されています。
Windowsの場合
USBを接続して「エクスプローラー」を開きます。ここで「完全なフォーマット」を実行することで、上書き処理付きの初期化が行われます。
- ①USBメモリのアイコンを右クリック
- ②「フォーマット」を選択
- ③「クイックフォーマット」のチェックを外し、「開始」をクリック
※処理完了まで時間がかかります。
上記の手順を踏むことで上書き処理付きのフォーマットが行われ、単純削除より復元されにくい状態にできます。必要に応じて、専用ソフトでの上書き処理(書き換え)を併用すると、さらに復元されにくくなります。
Macの場合
USBを接続して「ディスクユーティリティ」を開きます。ここで完全なフォーマットを実行することで、上書き処理付きの初期化が行われます。
- ①「アプリケーション」>「ユーティリティ」フォルダ内にある「ディスクユーティリティ」をクリック
- ②消去したいUSBを選択し、消去ボタンをクリック
消去の際に表示される「セキュリティオプション」の設定画面で、「ゼロ消去」や「上書き消去」を選択することで、上書き回数やセキュリティの安全度レベルを調整できます(macOSのバージョンによっては表示されない場合があります)。必要に応じて、専用ソフトでの上書き処理(書き換え)を併用すると、さらに安全です。
専用ソフトを使って消去する
WindowsやMacに対応したデータ消去専用ソフトを使用する方法です。市販されている削除用ソフトは、データに乱数などを入れ込み上書きする仕組みで、通常の方法ではデータが読み込めなくなります。複数回上書きすることで復元されるリスクを大幅に減らすことができ、家庭でも手軽に実施できます。
ただし、完全にデータが削除されたかどうかを保証することはできません。個人用途であれば十分安全ですが、機密性の高い情報を扱う場合には、物理的破壊や専門業者による消去の併用が望ましいです。
粉々に粉砕する
物理的に破壊する方法で、比較的簡単に行える手段です。USBの基板やチップをハンマーなどで粉砕し、元の状態に修復不可能と言えるレベルまで破壊することが重要です。特に、基板の上にある黒いチップをしっかり粉砕するようにしましょう。
注意点として、数回割っただけでは内部の小さい記憶領域が残っている可能性があり、その場合はデータの復元ができる場合があります。また「差し込んでも反応しない」「USB自体が壊れている」といって何もせず処分するのはおすすめできません。故障の原因がUSBではなく使用しているパソコン側にある可能性もあります。
作業する場合は、安全のため手袋や保護眼鏡を着用し、破片の飛散に注意してください。法人の場合は、専門業者に依頼すると廃棄証明書も発行してもらえるため、安全性と証明の両面で安心です。
CD・DVDのデータを読み取れなくする方法
CDやDVDは、パソコンなどの機器に入れても読み取れない状態にすることが重要です。USBと違い、CD・DVDは物理的に破壊するだけでデータを読み取れなくすることができます。ここでは代表的な方法を紹介します。
CD・DVDにハサミやカッターで傷を入れる
CDやDVDの記録面にハサミやカッターで深い傷を入れることで、データが読み込めなくなります。これは、不要になったディスクを最も手軽に処分する方法のひとつです。傷を入れる際は、ディスクの中心から外周に向かって複数箇所に入れると効果的です。ただし、完全に読み取れない状態になるよう、十分に深く傷をつける必要があります。
CD・DVDをシュレッダーで粉砕する
CD・DVD用のシュレッダーを使うと、粉砕されて物理的にデータを読み取れなくできます。家庭用やオフィス用の専用シュレッダーは、ディスクを小片に裁断するタイプが多く、破片の大きさが小さいほど復元のリスクは低くなります。作業中は破片が飛び散るため、手袋や保護眼鏡を使用することをおすすめします。
CD・DVDの記録層を破壊する
CDやDVDは、透明なプラスチック層の下に金属の記録層があります。この層を破壊することで、読み取り不能にできます。例えば、ディスクを曲げて割る、表面を強く擦る、あるいはドリルで穴を開けるといった方法があります。ただし、データを確実に消去するためには、破壊の際は十分に記録層まで損傷させることがポイントです。
USB・CD・DVDの処分方法の選び方

USBやCD・DVDの処分方法には、物理破壊やパソコン上でのデータ消去、そして専門業者への依頼など、さまざまな選択肢がありますが、処分する量が多い場合や、機密性の高い情報を扱う場合は、専門業者に依頼することをおすすめします。
業者によって対応できる媒体の種類や処分方法、費用、廃棄証明の発行の有無などに違いがあり、メリット・デメリットがあるため、依頼する際は、これらの条件を事前にしっかり確認しましょう。無料や低価格で引き取ってくれる業者の場合は、どのような方法でデータを消去するのか、廃棄証明が発行されるかなどを必ず確認し、安全性や信頼性を見極めることが重要です。
各種メディアを処分・廃棄する際のおすすめの機密抹消サービス
ここでは、業者への依頼を検討している方におすすめの日本パープルの機密抹消サービスをご紹介します。
家庭では処分しきれない大量のメディアや、企業の機密情報が入ったUSB・CD・DVDなども、安全かつ確実に処理してもらえるサービスです。
処理後に、機密抹消証明書を発行するのはもちろんのこと、処理前後の写真を添付し、HDD・SSDや本体のシリアル番号を記載して、どの機器がいつ処理されたかを追跡できるようにしています。企業のコンプライアンスや内部監査でも安心です。
ポイント① VHSからメモリーカードまであらゆる媒体に対応
CD・DVD・MO・VHS・フロッピーディスク・マイクロフィルム・各種メモリーカード・USBメモリ、デスクトップPC、ノートPC、サーバ(NAS)、外付けドライブ、タブレット端末、UPS、液晶ディスプレイ、スマートフォンなど、ほぼすべての記録メディアに対応しています。自宅やオフィスで散乱しがちな古いメディアもまとめて処分可能なので、手間をかけずに安全な廃棄が可能です。
ポイント② 完全破砕処理で情報復旧の可能性0%
配送中や保管庫での情報漏えいを防ぐため、ハイレベルなセキュリティ環境が整っています。処理は、米国防総省の基準を満たした磁気消去装置や専用破砕装置を用い、HDD・SSDは穿孔や圧迫破壊、V字破壊などの物理破砕処理を行います。これにより、データの復元はほぼ不可能となります。
また、処理施設は24時間の監視体制やゲート式金属探知機、不審者事前検知システム(DEFENDER-X)を導入。運搬時も完全密封車で輸送し、全車両にGPSを搭載するなど、情報漏洩リスクを徹底的に排除しています。
日本パープルはISO27001(ISMS)およびプライバシーマーク認証を取得し、情報セキュリティマネジメントを継続的に運用しています。回収スタッフも全員が社内の機密保持審査をクリアした上で、研修を受けており、安心して依頼可能です。
ポイント③ 処理後はリサイクルして燃料に変身
プラスチックなどの廃棄物を焼却する際に発生する熱を熱エネルギーとして再利用したり、加工して石油や石炭の代替燃料へ変換したりする「サーマルリサイクルが行われます。安全に処分しながら、環境にも配慮したリサイクルが可能であることも、大きな特徴のひとつです。
機密情報は確実に消去してから廃棄しましょう
USBやCD、DVDなど一見小さなメディアでも、会社で使用していたものは機密物として扱わねばなりません。廃棄の際は、適切な処理を行うことが自社の情報セキュリティを守ることに繋がります。社内で行うことが不安な方は、今回ご紹介した専門業者などに相談することも選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。