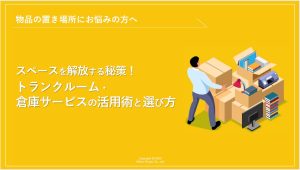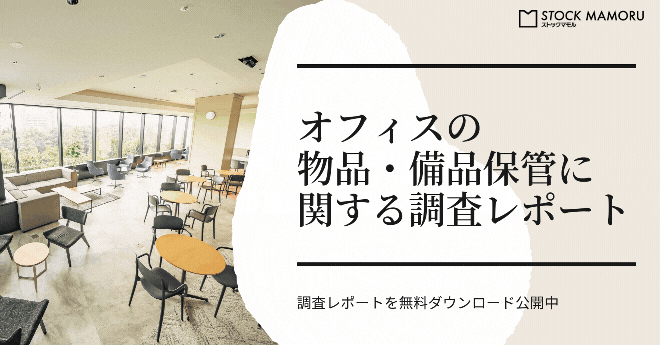オフィスの物品整理のコツ!片付け・整理整頓のアイデアを解説
オフィスの物品整理のコツ!片付け・整理整頓のアイデアを解説
オフィスの物品整理や片付けに頭を悩ませていませんか?
日々の業務の中で書類や備品が増えていくと、整理整頓が後回しになりがちです。しかし、オフィスが散らかったままでは、仕事の効率が下がるだけでなく、来訪した顧客や取引先に対してもマイナスな印象を与えかねません。
「オフィス整理は面倒」「片付けの時間が取れない」と感じる方も多いかもしれませんが、実はちょっとしたルール作りや工夫を取り入れることで、誰でも無理なく整理整頓を習慣化することが可能です。
本記事では、オフィスの物品整理をスムーズに行うためのコツや、チームで取り組める整理整頓のアイデアをわかりやすくご紹介します。業務効率の向上にもつながる整理術を、ぜひ参考にしてみてください。
オフィス物品の整理が生産性を上げる理由
物品や書類が散乱し、どこに何があるか分からない状態のオフィスでは、社員が本来の業務に集中できず、無駄な作業や時間が発生してしまいます。一方で、整理整頓が行き届いた職場環境では、業務の効率が格段に向上し、社内のコミュニケーションもスムーズになる傾向があります。
とはいえ、業務優先の現場では「オフィスの整理」は後回しにされがちです。ですが、オフィス物品の整理は単なる片付けではなく、企業全体の生産性に直結する重要な業務の一つです。
ここでは、整理整頓がどのように無駄を減らし、結果的に生産性を高めるのかを詳しく見ていきましょう。
整理がもたらす3つの無駄削減効果
オフィスの物品整理によって得られる最大の効果のひとつが、「無駄の削減」です。以下の3つの観点から、整理整頓がいかに重要かを具体的に解説します。
- 探す時間の削減
資料や備品の場所が明確であれば、必要なものを探す時間が大幅に短縮されます。1人が1日に数分探し物をするだけでも、1か月、1年単位で見れば膨大な時間が失われていることになります。整理によって業務に集中できる時間が増え、業務効率が大幅に改善されます。 - スペースの有効活用
不要な書類や古い備品を処分することで、オフィスに空間が生まれます。限られたスペースを有効活用できるようになれば、新たな作業スペースの確保や、レイアウトの見直しによる環境改善も可能になります。つまり整理整頓は、コストをかけずに職場の快適性を向上させる手段でもあるのです。 - ミスの防止
情報や物品が混在している環境では、古い資料を使ってしまったり、使いかけの在庫を無視して新しく注文してしまうなどのミスが起こりやすくなります。整理された状態を保つことで、業務の正確性が向上し、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
整理整頓が企業にもたらすメリット
オフィス物品の整理整頓は、個人の仕事のやりやすさだけでなく、企業全体にさまざまなメリットをもたらします。
- 生産性の向上
整理された職場では、社員一人ひとりが業務に集中しやすくなり、結果としてチーム全体のパフォーマンスが底上げされます。 - 職場の雰囲気改善
スッキリと整ったオフィスは、見た目にも清潔で快適な印象を与えるため、社員のモチベーション向上や来訪者への印象アップにもつながります。 - 業務の標準化と属人化の防止
整理整頓のルールを明確化・共有することで、「誰がやっても同じように仕事が進む」体制が整います。結果として、特定の人に業務が偏る“属人化”を防ぐ効果も期待できます。 - コスト削減
不要な備品や在庫を抱えることが減るため、無駄な購入を防ぐことができ、コスト面でもメリットがあります。
このように、整理整頓は単なる“清掃”や“片付け”ではなく、経営的な視点から見ても効果の高い取り組みです。継続的な改善の第一歩として、オフィスの物品整理に本気で取り組んでみてはいかがでしょうか。
オフィス物品整理の基本ステップ

オフィスの整理整頓は、ただ物をきれいに並べるだけではありません。
使いやすさや働きやすさを高めるために、物の“量”や“場所”を見直し、効率的なオフィス環境をつくるための重要な取り組みです。
まずは、基本となる整理の進め方を押さえておくことが大切です。ここでは、実際の整理作業の流れと、実践を成功に導く3つのポイントをご紹介します。
整理の4ステップ:「出す」「分ける」「減らす」「しまう」
オフィス物品を効率よく整理するには、基本となる4つのステップがあります。
それは「出す」→「分ける」→「減らす」→「しまう」です。
まずは、対象となる物品をすべて取り出して現状の量を把握します。日常的に使っているものだけでなく、奥にしまわれて存在を忘れていたものなども含めて、現状を“見える化”することがスタート地点です。
次に、それらを「使っている物」「今後も必要なもの」「不要なもの」に分別し、不要なものは思い切って処分します。このとき、「今は使っていないが、いつか使うかもしれない」という曖昧な判断は整理の妨げになります。整理とは「捨てること」と言っても過言ではありません。「迷ったら捨てる」くらいの気持ちで判断することが、整理の成果を高めるポイントです。
不要な物を減らし、必要なものだけを選別したら、最後はそれらを「しまう」ステップ。ここでは、使いやすさや取り出しやすさを意識した収納場所を決めることで、維持管理がしやすくなります。
このように、ただ片付けるだけでなく、「減らす」ことに重点を置くことで、整理の効果は何倍にもなります。
整理を成功させる3つのポイント
オフィスの整理整頓を継続的に成功させるためには、具体的な「コツ」を押さえることが大切です。
ここでは、オフィス物品の整理をスムーズに進める上で押さえておきたい3つの重要なポイントを紹介します。
1. 見える化する
物品の「見える化」は、無駄をなくし業務効率を高める第一歩です。
どこに何があるかが一目ですぐに分かる状態にしておくことで、探す手間や時間の削減にもつながります。
最近では「見せる収納」のように、あえてオープンに物品を配置するスタイルも注目されています。
また、整理の一環として、定期的に断捨離を行い、物の総量を減らす習慣を持つこともオフィス整理につながります。
2.不明なものをなくす
オフィス整理の妨げとなる代表的な要因が、「正体不明のもの」の存在です。
特に、所有者が分からない物品や、用途が不明な書類などは、勝手に処分できず放置されがちです。
「一時的に置いたまま忘れられたもの」や「いつか使うかもと取ってあるもの」がオフィスのスペースを占領していないでしょうか。
それらは、そのまま放置されることで“無主物”化し、処分しにくくなります。
もし3年以上使用していないものがあれば、それは処分対象と考えて良いものかもしれません。
3.ルール化して習慣にする
整理整頓を一時的な活動で終わらせないためには、「ルール化」と「習慣化」が不可欠です。
どれだけキレイに整理整頓しても、ルールが決まっていなければオフィスは時間の経過とともにすぐに元の状態に戻ってしまいます。
たとえば、「〇〇はこの棚に収納する」「使った後は元の場所に戻す」「週に1回は棚を見直す」など、具体的なルールを決めておくことで、日常の中に整理を取り込むことができます。
収納場所やルールを設定したら、それを必ずオフィスメンバー全員で共有することが大切です。誰が見ても同じように整理ができる状態を目指しましょう。
ルールを定着させて習慣化すれば、整理された状態が自然と継続できるようになります。
すぐに実践できる!オフィス整理の具体的なアイデア
オフィスの整理整頓は、「やろう」と思っていても、具体的に何から始めればいいのか悩みがちです。
ここでは、今日からすぐにでも取り入れられる具体的な整理のアイデアを6つ紹介します。
実際のオフィスに合わせてアレンジしながら実践してみてください。
1. 透明収納で“見える化”を実現

小物や文具など、つい乱雑になりがちなアイテムは、透明な収納ケースを活用して“見える化”するのが効果的です。
アクリルボックスやクリアケースを使えば、中に何が入っているか一目で分かるため、「探す」時間が大きく削減されます。
さらに、誰が見ても中身が把握できることで、チーム内での共通認識が生まれ、収納ルールの徹底にもつながります。
視覚的に整っている状態は、整理されている印象を強く与え、外部からの印象も良くなるでしょう。
2. 定位置管理とラベリングで探さないオフィスへ
業務効率を高めるには、「どこに何があるか」が明確になっていることが重要です。
そのために有効なのが、物品の“定位置管理”と“ラベリング”です。
たとえば、棚や引き出しには中に入れる物の名前をラベルで表示し、誰でもすぐに把握・出し入れできるようにします。
ファイル、文具、工具、ダンボール、プリンター用紙など、あらゆる物品にラベルをつけておくと、「あれはどこ?」と誰かに聞く必要がなくなります。
さらに、収納場所の一覧をマップとしてまとめ、社内で共有しておくと、よりスムーズに運用できます。
新入社員や外部スタッフも迷わず使えるため、多くの企業が取り入れている手法です。
3. 収納エリアを一か所にまとめる
オフィス内の物品があちこちに散在していると、必要なものを探す時間が増え、生産性が下がります。
この問題を解消するには、できる限り収納場所は集約して設置し、「ここに来れば必要なものが揃う」という状態にしておくのがおすすめです。
物品の種類ごとに収納スペースを分散させるのではなく、ある程度まとめて集約することで、移動の手間も減り、管理の手間も大幅に軽減されます。
特にオフィスが広かったり複数フロアに分かれていたりする場合は、ゾーニングの見直しや模様替えによって、整理整頓のしやすい動線が生まれます。
4. 保管期限を決めて自動的に整理する仕組みを作る
整理において「ものを減らす」ことが大切だと述べましたが、加えて物品の保管期限を設定することでさらに効果が高まります。
たとえば、「この書類は保管期間3年」など、期限を明記しておくことで、一定期間が経過した物品は自動的に処分の対象になります。
この仕組みがあると、「捨てていいか分からない」という判断のストレスも軽減され、整理がスムーズに進みます。
期限をラベルや付箋などで見える形にしておけば、誰でも判断できるため、管理の属人化も防げます。
業務に支障が出ない範囲で、定期的な「期限切れチェック日」を設けるのも効果的です。
5. 書類はファイル、不定形物は蓋つきボックスに
紙資料が多いオフィスでは、書類整理のルールを明確にしておくことが欠かせません。
書類は必ずファイルで分類・整理し、表紙には「内容」と「保管期限」を明記しておくようにします。
書類サイズや形状がバラバラでファイルに収まらない場合は、蓋つきのボックスを活用するのが便利です。
蓋つきの収納なら中身が見えず、見た目にもすっきり整って見えるだけでなく、ホコリや汚れも防げます。
収納棚や足元スペースなどにボックスを活用し、ラベルで中身を示しておけば、取り出しも便利で、見た目と実用性の両立が可能になります。
6. トランクルーム・外部保管サービスの活用も検討
オフィス内だけでどうしても収まりきらない場合には、外部の保管サービスを活用するという手もあります。
特に、頻繁に使わないが捨てられない書類や備品などは、トランクルームや倉庫型の保管サービスで管理することで、オフィスのスペースを有効活用できます。
法人向けの外部保管サービスでは、セキュリティや空調管理が整っているところも多く、安心して保管できる環境が整っています。
一時的な保管だけでなく、長期的な書類アーカイブとして活用される企業も増えています。
「今使わないが必要なもの」と「今すぐ必要なもの」を切り分けて、適切な場所に配置することで、オフィスの“見える快適さ”をキープできます。
まだ使うかも?一時保管が必要な物品の扱い方
オフィス整理で多くの人が頭を悩ませるのが、「今すぐには使わないが、将来的に使うかもしれないもの」の扱いです。
捨てるには惜しいし、残しておいても場所を取る――そんな判断に迷う物品に対しては、“一時保管”という選択肢を上手に活用しましょう。
ここでは、処分に踏み切れない物品の扱い方や、スペースが足りない場合の対策について解説します。
処分に迷うものは“期限付き保管”が基本
「いつか使うかも」「また必要になるかもしれない」といった曖昧な理由で物を保管していると、整理は一向に進みません。
そのような場合は、“期限付き”で一時保管するルールを設けることが効果的です。
たとえば、「〇年〇月まで保管、以降は処分」といった明確な保管期限をラベルに記入し、見える場所に貼っておきましょう。
保管棚や倉庫の一角を“保留ゾーン”として設定し、その中で定期的に見直す仕組みをつくると、物が増えすぎるのを防げます。
さらに、保管する際には「中身」「保管日」「保管期限」「担当者」などを記録しておくことも重要です。
これにより、誰が見ても判断できる状態が保たれ、属人化を防ぎながら効率的な管理が実現できます。
社内スペースが足りないときは外部保管サービスを活用
「一時保管したいけど、そもそもオフィスに保管スペースがない…」という企業も少なくありません。
特に、近年ではオフィスの縮小・リモートワークの定着により、物品を置く場所自体が限られてきています。
そのようなときにおすすめなのが、トランクルームや外部の物品保管・管理サービスの活用です。
イベント用品や販促物、大型什器など、保管場所に困るアイテムも、外部サービスなら温度・湿度管理が整った環境で安全に保管できます。
また、法人向けのサービスでは、出し入れや在庫管理をオンラインで行えるところもあり、管理の手間を最小限に抑えることができます。
社内に保管スペースを無理に確保するよりも、コストや効率の面でメリットが大きい場合も多く、必要な時だけ引き出せる柔軟性も魅力です。
おすすめの保管サービス:Stock MAMORU(ストックマモル)

「社内に保管スペースがない」「いざという時にすぐ取り出せる仕組みが欲しい」といったお悩みを抱える企業におすすめなのが、日本パープルが提供する Stock MAMORU(ストックマモル) です。
ストックマモルは、単なる荷物の“保管”にとどまらず、「預ける・見る・取り出す・捨てる」という保管にまつわるすべての業務をトータルでサポートしてくれる法人向けサービスです。オフィスの整理やスペース最適化を検討している企業にとって、非常に頼れる存在です。
写真管理で「見える保管」を実現
ストックマモルの大きな特長のひとつが、「預けた荷物を写真で確認できる」という機能です。
保管中の物品は1点ずつ撮影され、Web上の管理画面に反映されます。
どこに何を保管しているのかが視覚的に把握できるため、「あれ、どこに預けたっけ?」という曖昧さがなくなります。
従来のようにリストや台帳で確認する必要がなく、まさに“見える保管”を実現している点が魅力です。物品の把握・共有がしやすくなることで、社内での情報伝達や判断スピードも向上します。
オンラインで出し入れ依頼が完結
ストックマモルでは、荷物の出し入れ依頼をすべてWeb上で完結することができます。
スマホやPCから管理画面にアクセスし、保管中の物品の中から出庫したいものを選ぶだけでOKで、あとは倉庫側が対応してくれます。これにより、社内での「取りに行く」「探しに行く」といった手間が不要になり、保管管理にかかる人件費や時間の削減にもつながります。
また、セキュリティと業務効率の両立が図れる便利な履歴管理機能もあるため、いつ・誰が・どの物品を出し入れしたのかも簡単に追跡可能です。
専門スタッフによる集荷と梱包対応
「荷物を預けたいけど、まとめて運ぶのが大変…」という場合も、ストックマモルなら安心です。
専門のスタッフが集荷・梱包まで対応してくれるため、依頼者側は準備の手間がほとんどかかりません。また、破損や混在を防ぐ丁寧な梱包を行ってくれるため、大切な資料や展示資材なども安心して預けられます。
業務の負担を最小限に抑えつつ、確実に保管業務をアウトソーシングできる点が、他の保管サービスと差別化される大きなポイントです。
セキュリティと利便性を両立した保管体制
ストックマモルの倉庫は、大手警備会社による24時間体制の監視セキュリティが導入されており、安全性の面でも高い評価を受けています。
機密性の高い書類や重要物品でも、安心して預けることが可能です。
また、温度・湿度などの環境管理も整っているため、デリケートな物品や長期保管に向いているものにも対応できます。
さらに、保管が不要になった物品については廃棄まで依頼可能なので、保管後の「その先」の対応も一貫して任せられます。
Stock MAMORU(ストックマモル)は、単なる「倉庫レンタル」ではなく、保管・可視化・運搬・処分まで一貫して任せられる、まさに“法人の保管部門”とも言える存在です。
荷物の増加にお困りの方、オフィス整理に行き詰まりを感じている方は、ぜひ一度導入を検討してみてはいかがでしょうか。
▶︎ Stock MAMORUの詳細はこちら
オフィス整理を定着させるためのコツ
オフィス整理は、一度整えただけで終わるものではありません。
きれいな状態を“維持”し、社員全体でその意識を共有しながら日常的に取り組んでいくことが大切です。
では、オフィス整理を一過性のイベントで終わらせず、組織に根付かせるにはどうすればよいのでしょうか?
ここでは、整理整頓を職場文化として定着させるための具体的な工夫をご紹介します。
社員全員でルールを共有し、意識改革を図る
オフィスの整理を成功させるには、一部の人だけが頑張っても意味がありません。
「全員参加」が前提です。
まずは、整理整頓に関する基本ルールを明文化し、全社員に周知しましょう。
例えば、「備品は使用後に元の位置に戻す」「保管期限をラベルに記入する」「週1回は共有エリアを点検する」といった、具体的で守りやすいルールを作ることがポイントです。
加えて、ルールをただ伝えるだけでなく、「なぜ整理が重要なのか」「整理が業務効率にどう貢献するのか」といった背景・目的まで共有することで、社員一人ひとりの意識改革にもつながります。
チーム内で整理の担当者を決める、定期的な“整理チェック”を設けるなど、習慣化させる仕組みをつくると、自然と整理の文化が根付いていきます。
定期的な見直しで「片付いた状態」を維持する
整理整頓は“始めること”よりも、“続けること”の方が難しいものです。
一度きれいに整えたオフィスも、気づけば元通り……というケースも少なくありません。
そのためには、定期的な見直しの機会を設けることが不可欠です。
たとえば月に1回、クリーンデーや整理チェック日を設定し、不要な物品が増えていないか、ルールが守られているかを確認する習慣を持ちましょう。
見直しの際には、「改善点」「維持できている点」をチーム内で共有し、小さな成功体験を積み重ねていくことも大切です。
こうしたサイクルを繰り返すことで、整理は自然と日常業務の一部になり、“片付いていて当たり前”という意識が定着していきます。
まとめ|オフィス整理のコツを実践して生産性を高めよう
オフィス整理は、ただ“片付ける”だけの行為ではなく、無駄を省き、仕事の質を高めるための重要な施策です。
物品の所在が明確になり、探す時間が減ることで業務の効率は向上し、スペースの有効活用やミスの防止にもつながります。
そのためには、「出す・分ける・減らす・しまう」の基本ステップに加え、見える化やルール化などの具体的な工夫を取り入れ、社員全員で整理整頓の意識を共有することが欠かせません。
また、一時保管や外部サービスの活用など、社内の状況に応じた柔軟な対応も有効です。
オフィス整理は一度で終わるものではありませんが、継続しやすい仕組みを整えれば、“整った状態”を当たり前にできる職場づくりが実現します。
ぜひ今回ご紹介したコツやアイデアを参考に、オフィス環境の改善から生産性向上を目指してみてください。
オフィス物品整理に関するお役立ち資料はこちら