機密書類の保管方法は?安全に保管するポイントや廃棄方法などを解説

契約書や設計図が机に山積みで、「どの書類を残し、いつ廃棄すべきか分からない」と悩んでいませんか?
機密書類の扱いを誤ると、取引先の信頼低下や巨額の損失といった深刻なリスクを招きます。
この記事では、重要度別の保管ルール策定方法、社内外で安全に管理する具体策、法定保存期間の把握から保存期限を迎えた文書を確実に廃棄する手順までを分かりやすく解説します。
さらに、限られたオフィススペースでも実践できるキャビネット管理のコツや、セキュリティ要件を満たす外部保管サービス選定のチェックリスト、廃棄時に発生しやすい漏洩リスクを防ぐポイントも解説します。
実務に直結する情報管理体制を見直したい方は、ぜひ参考にしてください。
機密文書とは?
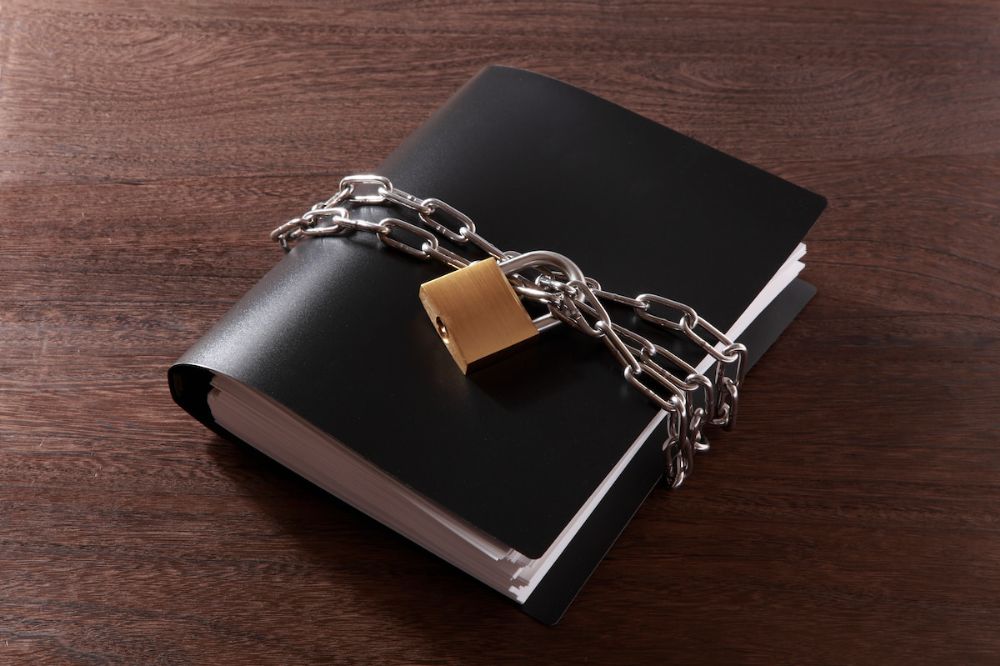
会社にとって重要な文書を、総じて機密文書と言います。
財務情報や製品に関する情報、顧客情報なども機密文書に該当します。重要性が非常に高いことから、漏洩した場合は会社にとって大きな損失となります。社内の一部の役員しか閲覧できない書類もありますが、一般社員が取り扱う書類も含まれます。そのため、全社員が機密文書に対する取り扱いについて理解しておく必要があります。
以下で、機密文書が持つ役割や漏洩のリスクについて、具体的に解説します。
機密文書の役割
機密文書は、その文書の重要性を認識させることに大きな役割があります。機密文書となることで文書に対して慎重に取り扱うことを意識するようになります。漏洩や紛失のリスクが低くなります。また、誤って破棄してしまうリスクも下げることができます。
機密文書の取り扱いに関するマニュアルを作成し、社内で共有することが重要になります。
機密文書の外部漏洩のリスク
機密文書が外部漏洩した場合、様々なリスクが生じる可能性があります。
機密文書に取引先の情報や取引の履歴も含まれていますので、取引先からの信用を失い、会社としての信用を失うことにつながります。さらに、SNSやネットニュースによって拡散されることで、「外部漏洩があった企業」というイメージが定着してしまう可能性があります。マイナスなイメージが定着すると、株価が下がり、最悪の場合倒産してしまうケースもあります。
情報漏洩に関するお詫びや謝罪広告に関する費用によって莫大な損害が発生した事例もあるため、機密文書の管理や保管には細心の注意を払う必要があります。
機密文書は3つのレベルに分けられる
機密文書の種類は企業に関する事、取引先に関する事、個人情報に関する事の3つに分けることができます。また、重要度のレベルに合わせて以下の3つに分類することができます。
- ・極秘文書
- ・秘文書
- ・社外秘文書
それぞれの文書の特徴について、以下で詳しく解説します。
極秘文書
極秘文書は、機密文書の中でも最も慎重に管理を行わなければいけない文書で、3つの中で最も重要度が高いとされています。
具体的には、企業の財務や経理に関する情報、顧客に関する情報、新製品の設計図や研究データなどが該当します。閲覧できるのは、社内でも一部の限られた社員のみとなっています。極秘文書が外部に漏洩すると、会社の利益に多大な損害を与える可能性が高いです。
外部への漏洩を防ぐために、関係者以外が入れない場所で、なおかつ鍵付きの保管庫やキャビネットなどで保管や管理を行う必要があります。また、管理や保管を誰が行うかを明確にし、所在地も定期的に確認しておくようにしましょう。
秘文書
秘文書は、極秘文書の次に重要とされる機密文書です。
重要度は極秘文書と比較すると低いですが、漏洩してはいけない重要な情報が含まれているので、重要度が高い文書であることは間違いありません。具体的には、各種契約書、人事評価に関する資料、販売やコストに関する情報などが該当します。閲覧できるのは当該業務に関わる社員のみで、社内全体で共有することは禁止されています。
保管や管理を行う際は、極秘文書と同様に関係者以外が閲覧することができないように、十分注意する必要があります。
社外秘文書
社外秘文書は、閲覧が社内に限定されており外部への漏洩が禁止されている文書です。
極秘文書や秘文書と比較すると重要度は低いですが、外部に漏洩すると会社としての信用が低下する可能性があります。具体的には、会議議事録や業務マニュアル、社内向けの資料などがあります。
あくまでも、他の2つと比較すると重要度のレベルが低くなるだけなので、重要な書類であることに変わりはありません。そのため、社外に漏洩しないように保管・管理を行う必要があります。
機密文書の保管のルール
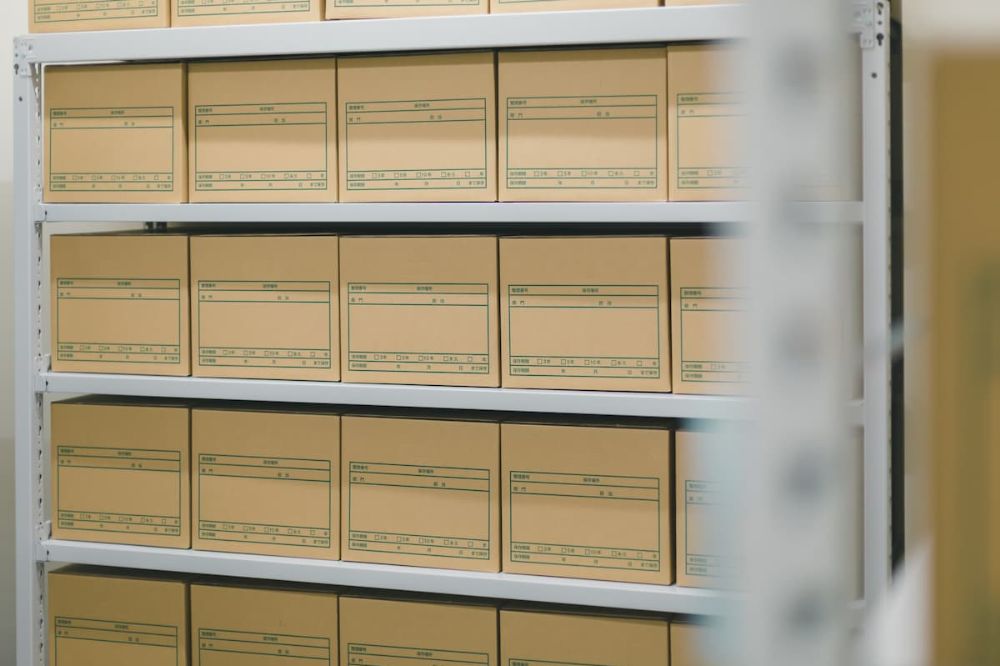
機密文書の保管のルールを定めるにあたり、意識しておくべきポイントがあります。
以下で、具体的に見ていきましょう。
機密文書の保管期間
機密文書の多くは法で定められた保管期間があり、「法定保存文書」とも呼ばれます。
法的な保存期間がある場合はそれに従いますが、保管期間が定められていない文書もあります。たとえば、企画書や見積書などは法的な保管期間がありません。そういった場合は、会社で独自にルールを設定する必要があります。法的なルールが無いからといって廃棄しないままにしておくと、次々に書類がたまってしまい、業務に支障が出る可能性があります。廃棄のタイミングを設定しておけば、文書の管理を適切に行うことができるでしょう。
社内でのルール策定
機密文書の取り扱いについては、社内でルールを策定することが重要です。
社内でルールを徹底させることで、社内での機密文書の取り扱い方を統一させることができます。外部露営や紛失などを防ぐために、ルールの策定は大きな役割を果たしています。誰が管理を行うのか、閲覧可能な時間帯はいつか、管理されている場所はどこか、といったポイントをルールに記載すると良いでしょう。
機密文書の保管・取り扱いの社内ルールの必要性
機密文書の保管・取り扱いにおける社内ルールの必要性として、以下の3つがあげられます。
- ・機密文書の紛失リスクの防止
- ・機密文書の情報漏洩の防止
- ・作業の効率化につながる
それぞれどういった点から必要なのか、以下で見ていきましょう。
機密文書の紛失リスクの防止
社内ルールで保管方法を明確にして、社内全体で適切な方法を共有することで、紛失リスクを防止することができます。
機密文書が紛失すると、文書に記載されている重要な情報を社内で共有することができなくなる可能性があります。また、文書に記載されている重要な情報が第三者の目に触れるリスクもあります。
機密文書の情報漏洩の防止
機密文書の情報が漏洩すると、会社や取引先などに関する重要な情報が外部に知られることになります。取引先からの信頼を失うだけでなく、会社としての信頼を失う可能性もあります。
社内ルールにおいて情報漏洩の禁止を明確にし、十分に周知することが重要です。周知することで、徹底的な情報漏洩対策を行うことができます。
作業の効率化につながる
保管や取り扱いの方法がルール化されていると、何をどのような順番で行えばいいかが明確になるため、作業を効率化することができます。
効率化することで、他の業務に割く時間を増やすこともできるようになるため、社内全体の業務効率を向上させることができます。
機密文書の保管方法・ポイント

機密文書の保管方法としては、社内での保管か、保管サービスを利用するかのどちらかになります。以下で、それぞれの保管方法やポイントについて確認しましょう。
社内での保管
社内に機密文書を保管するスペースがある場合は、社内で保管を行う会社が多いです。
専用の文書保管室で保管する会社もあれば、鍵付きのキャビネットや引き出しを利用する会社もあります。文書の量が増えると社内のスペースが狭くなってしまいますが、必要な時にすぐに取り出せることから利便性は高いと言えます。
文書保管室があれば、文書を大量に保存することができます。また、長期的な保存が必要な文書や普段あまり利用しない文書の保存にも向いています。
鍵付きのキャビネットや引き出しは、少量の文書を保存するのに向いています。極秘文書の場合は、なるべく人の目に触れないように、役員室の鍵付きのキャビネットなどで保管するようにしましょう。また、仕事で利用する頻度が高い文書は、退社時にキャビネットや引き出しに鍵がかかっているかどうか、確認を忘れないようにしましょう。
保管サービスの利用
スペースが足りない、セキュリティが不十分、なども理由で社内で機密文書の保管や管理を行うことが難しい場合もあります。
そのような場合は、外部の保管サービスを利用するのが便利です。保管サービスに預けることで、紛失や漏洩によるリスクが高い文書を安全に保管することができます。保管サービスを選ぶ際は、セキュリティ対策や保管環境などに注目して選ぶことが重要です。選ぶポイントに関しては、後ほど詳しく解説します。
機密文書の廃棄について
機密文書は。保存期間が過ぎたら廃棄を行う必要があります。
廃棄前の確認事項や破棄する際の方法について、以下でチェックしましょう。
廃棄前の確認事項
廃棄前に、その文書の保管期間が何年になっているかを改めて確認しましょう。
保管期間が過ぎていることが確認できれば、廃棄を行うことができます。保管期間を過ぎる前に誤って廃棄してしまうと、必要になった時に用意ができないという事態になります。特に税務関係の書類は、税務署に入出金の根拠を示すために必要なため、使途不明金として扱われる可能性が高くなります。
誤って廃棄することを防ぐために、保管期間は必ず確認するようにしましょう。
廃棄方法の確認
廃棄方法をどのように行うか、事前に確認しておくことも重要です。
シュレッダーで廃棄を行っている会社が多いですが、情報漏洩は廃棄のタイミングで発生することが多いため、可能な限り細かくするなど工夫が必要です。シュレッダー以外の方法として、機密文書廃棄を専門に行うサービスを利用している会社もあります。
機密文書の保管サービスを選ぶ際のポイント

機密文書の保管サービスを選ぶ際のポイントは、以下の4つです。
- ・セキュリティ・保管環境
- ・保管期間を確認できるか
- ・預け入れ・取り出しのしやすさ
- ・廃棄サービスの有無
以下でそれぞれのポイントについて解説しますので、参考にしてみてください。
セキュリティ・保管環境
セキュリティや保管環境がどのようになっているかは、選ぶ際のポイントとして重要です。
監視カメラ、入退室管理システム、防火システムなどセキュリティ対策や保管環境が充実していれば、情報漏洩や盗難、紛失などのリスクが大幅に下がります。
保管期限を確認できるか
保管期間を確認することができるかどうかも、チェックしておきたいポイントです。
期間を過ぎた機密文書は、速やかに廃棄する必要があります。保管期間を確認することができれば安全に管理がしやすくなり、適切なタイミングで廃棄を行うことができます。
預け入れ・取り出しのしやすさ
預け入れ・取り出しがしやすいかどうかも確認しておきましょう。
文書の預け入れや取り出しまで一括で行ってくれるサービスであれば、会社側の負担を減らすことができるので便利です。
廃棄サービスの有無
廃棄サービスがあるかどうかのチェックも、重要なポイントです。
文書の廃棄サービスがあれば、保管期間が過ぎた機密文書を確実に廃棄してくれます。廃棄は溶解処理やシュレッダーなどで行われ、漏洩のリスクを可能な限り低くする方法が用いられます。
機密書類の保管方法のまとめ

機密文書には様々な種類があり、重要度によって分類されています。重要度の違いはありますが、外部に情報が漏洩しないように、適切に保管・管理しなければいけない点は共通しています。
様々な事情で社内で機密文書を保管することが難しい場合、保管サービスを利用するという方法もあります。
外部サービスの利用を検討している方にとって、この記事で解説した内容がご参考になれば幸いです。






















