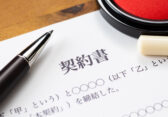書類だけじゃない!廃棄に注意が必要な機密物品と処理方法を解説

機密の情報の処理というと紙の書類ばかりが注目されがちですが、社内には他にもさまざまな機密物品が存在しています。例えば、社員の個人情報が分かるような社員証やIDカードなどは、情報漏えいにつながる機密物品です。
情報漏えいは企業の信用や存続に関わる重大なリスクですので、会社として十分に対策する必要があります。また、企業から出る廃棄物は家庭ごみのように簡単に捨てることができないため、書類・物品それぞれに適した廃棄方法を理解しておく必要があります。そこで本記事では、廃棄に注意が必要な機密物品の種類と、正しい処分方法について解説します。
書類以外に廃棄に注意が必要な機密物品
書類の廃棄にはシュレッダーを使用することが当然という認識が広く浸透していますが、書類以外の機密物品については、処分の重要性が見落とされがちです。書類以外の機密物品について、明確な処分ルールが設けられていないケースも少なくありません。ここでは、社内に存在する代表的な機密物品と、それぞれ廃棄時に注意すべき理由について解説します。
社員証やIDカード

社員証やIDカードには、氏名・所属部署・社員番号・顔写真など、個人を特定できる情報が含まれています。これらが外部に流出すると、なりすましによる不正入館や情報窃取に悪用される恐れがあり、セキュリティ上の重大なリスクとなります。磁気ストライプやICチップが付いたカードを読み取り可能な状態で捨てるのは特に危険です。退職時などには返却する物品のリストに入れておかなければならないのは言うまでもありません。
印鑑

会社名が刻まれた角印や代表者印などは、企業の意思決定を証明する重要なツールです。不要になった印鑑でも、そのまま保管・放置・廃棄してしまうと、文書の偽造やなりすまし契約など、深刻な不正利用につながる可能性があります。
開発中のプロダクト

試作中の製品や未発表の技術資料、デザインモックなどは、企業の競争優位性を左右する情報を含んでいます。これらが流出すると、アイデアや技術の模倣、特許侵害、リークによる信用失墜といったリスクが生じます。仮に失敗作であったとしても、簡単にごみ箱に入れてしまうのは危険だといえます。
鍵

社内設備や書庫、ロッカー、サーバールームなどの物理的なアクセス手段である鍵は、万一外部に漏れれば、不正侵入や盗難といった深刻な被害を引き起こします。もう使わなくなった扉の鍵であったとしても事件に繋がりかねません。
ユニフォーム
会社ロゴや所属情報が入ったユニフォームは、組織の一員であることを示す外見的な証明になります。転売・悪用されると、なりすましや信用の毀損につながる恐れがあり、特にセキュリティが求められる業種では大きな問題となります。
各種メディア(CD、DVD、USBメモリ)
これらのメディアには、顧客情報・設計データ・社内文書などのさまざまな機密データが保存されている可能性があります。単に削除するだけではデータは完全に消去されず、復元されるリスクがあります。
パソコン・HDD・サーバー
業務で使用されていた端末やストレージ機器には、過去のやり取り・業務資料・社内システム情報が大量に保存されています。これらを適切に管理せず処分すると、内部情報の漏えいや不正アクセスを招く恐れがあります。
スマートフォン・タブレット
スマホやタブレットも、メール、チャット履歴、アプリデータなど、業務に関する重要な情報を大量に含んでいます。端末内のデータは初期化だけでは完全に消去されないことがあり、モバイル端末の廃棄には特に慎重さが求められます。
廃棄に注意が必要な各物品の処理方法

書類以外の機密物品は、情報の性質や媒体の違いによって適切な廃棄方法が異なります。ここでは、前項で取り上げた各物品について、漏えいリスクを防ぐための具体的な処理方法を解説します。
社員証やIDカード
社員証やIDカードは、物理的に裁断・破壊し、再利用できない状態にするのが基本です。ICチップや磁気ストライプ付きのカードは、専用のカードシュレッダーやカッターでチップ部分を含めて完全に処分します。
紙以外のものを裁断するシュレッダーの性能は近年改善されていますが、まだまだセキュリティ面での不安が残ります。完全に処理するには、セキュリティ対応済みの廃棄業者へ委託して破砕や溶解処理を利用することをおすすめします。
印鑑
会社の実印を廃棄することになったら、まず法務局で印鑑・印鑑カード廃止届書を提出し、直近で使用していた場合は取引先にも一報を入れておきましょう。会社認印は特に事前の書面上の手続きはないものの、こちらも関係者に周知しておくことをおすすめします。会社銀行印の場合は、事前の変更手続きが必要です。
不要となった印鑑は、彫刻面を削る、砕く、焼却するなど、原形を留めないように処理する必要があります。社判・代表印など重要度が高い印鑑ほど、処理の記録(廃棄証明)を残すことが求められます。処理を委託する際は、印鑑類の取り扱い実績がある業者を選びましょう。
開発中のプロダクト
試作品や試作部品などは、分解・破壊して再利用できない形にし、設計図や関連文書と合わせて厳重な機密処理を行います。産業廃棄物として処理する場合は、マニフェストの管理や機密保持契約の締結が必要なケースもあります。
鍵
鍵の一般的な処分方法としては、折る・割るなどしてから廃棄するとよいと言われていますが、法人の場合、セキュリティ面を考慮するとこれでは不十分かもしれません。金属破砕機などで物理的に破壊し、原形を留めない状態にしてから廃棄するのが安全です。オフィスビルや重要設備の鍵などは、廃棄証明の取得を推奨します。社内で難しい場合は、セキュリティ専門業者に委託することで確実性を高められます。
ユニフォーム
ロゴや企業名が入ったユニフォームは、裁断・切り刻むなどして再利用できないようにします。枚数が多い場合や素材に難がある場合は、業者による焼却・溶解処理を選ぶのが一般的です。廃棄証明書の発行が可能な業者を利用すれば、社内管理の透明性も確保できます。
廃棄に関わる関係者を限定することや機能破壊(復元不可能な状態に破壊する)、保管場所の要件確認・厳重管理、警備の徹底など、厳密に管理をすることが求められています。
各種メディア(CD、DVD、USBメモリ)
CDやDVDは物理的に割る・破砕するのが基本です。USBメモリなどは、ソフトウェアによる完全消去を実施したうえで、物理的破壊を行います。社内で処理が難しい場合は、機密メディア専門の廃棄サービスを利用することで、確実なデータ抹消が可能です。
パソコン・HDD・サーバー
これらの機器は、まずデータを完全消去(専用ソフトウェアやDegauss処理など)し、その後HDDやSSDの物理破壊を行います。サーバー本体は資産価値がある場合もあるため、リユースを検討する場合でもデータ抹消証明書の取得が必要です。大量処分時は専門業者の回収・処理サービスを活用するのが確実です。
スマートフォン・タブレット
スマホやタブレットも、工場出荷時リセットでは不十分な場合が多く、専用ソフトによるデータ消去+物理破壊が推奨されます。業務用端末には多くの機密情報が残っているため、処理履歴を明確にするためにも、データ消去証明の取得や処理の委託先選定が重要です。
外部サービスの活用も検討
書類以外にも注意すべき物品がこんなに多いことに驚かれた方もいるのではないでしょうか。たとえ小さな鍵一つであっても、適切に処理されていなければ情報漏えいやセキュリティ事故に繋がる可能性がありますので、しっかりと対策を行わなければなりません。とはいえ、各物品の特性を踏まえたセキュリティリスクを低減させる必要があり、廃棄には多くの手間やコストがかかることに悩まれている担当者も多いようです。特に対応が煩雑になりがちな複数種類の機密物品を一括で安全に処理したいというニーズは高まっています。
そこでおすすめするのが、専門業者による機密物品の処理サービスです。ここでは、幅広い機密物に対応し、セキュリティ体制にも定評のある日本パープルの機密処理サービスをご紹介します。
同サービスでは、書類・PC・HDD・USBメモリなどのデジタル媒体に加え、社員証・印鑑・鍵・ユニフォームなど、今回ご紹介したあらゆる機密物品に対応しています。完全密封輸送・立ち会い処理・廃棄証明書の発行など、安心して任せられる体制が整っています。
また、機密抹消サービスお客様満足度No.1などの実績が多数あり、企業の情報管理・コンプライアンス強化に貢献しています。
「社内での処理に限界を感じている」「処分方法がわからない」とお悩みのご担当者は、一度相談してみてはいかがでしょうか。
見落とされがちな機密物品を把握して、適切な処理を行おう
日々の業務で何気なく扱っている物品の中にも、重要な情報が含まれているものは少なくありません。社員証やUSBメモリ、鍵、ユニフォームなど、一見すると無害に見えるものでも、処理を誤れば情報漏えいや不正使用といった重大なリスクに繋がる可能性があります。
まずは社内にどのような機密物品が存在しているのかを洗い出し、その情報価値やリスクレベルに応じた処理方法を明確にすることが重要です。機密文書だけでなく、あらゆる「情報が付随する物品」を情報資産として捉え、社内ルールや廃棄フローの見直しを進めていきましょう。
社内対応が難しい・手間がかかると感じた場合は、信頼できる外部サービスを活用することも有効な手段です。処理の確実性だけでなく、証明書の発行や記録管理まで委託できるため、コンプライアンスや内部監査の観点からも安心感があります。
情報管理のリスクを最小限に抑えるためには、正しい知識と仕組みの整備が不可欠です。見落とされがちな機密物品を改めて見直し、安全かつ効率的な処分体制を整えていきましょう。