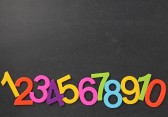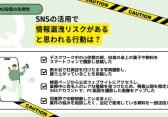プライバシーマークの基礎を解説!取得のメリットや手順も紹介

プライバシーマーク(Pマーク)とは、個人情報保護のためにきちんとリスク管理を行っている証明として企業に付与されるマークです。個人情報を多く扱う企業にとって、対外的に信頼性を示す手段となるため、個人情報を多く取り扱う企業ではプライバシーマークの取得を検討する機会もあるでしょう。
本記事では、プライバシーマークを取得するメリットや取得手順を解説します。また、プライバシーマークと個人情報保護法の関係についても紹介します。
プライバシーマーク取得を検討している企業の担当者様は必見です。
プライバシーマークとは
プライバシーマーク取得のメリット
プライバシーマークの取得手順
プライバシーマークの取得費用・取得期間
プライバシーマーク取得のポイント
プライバシーマーク取得には準備が必要
プライバシーマークとは

プライバシーマーク(Pマーク)とは、個人情報を適切に取り扱っている企業に与えられるマークです。一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運営する認証制度により付与されます。
認定を受けた企業は、一定の基準を満たして個人情報保護体制の整備や運用していると対外的に証明できます。
プライバシーマークの目的・重要性
プライバシーマーク制度の目的は、個人情報の適切な取り扱いの促進と、企業における情報管理体制の強化です。
現代社会では個人情報の漏えいや不正利用が頻発しており、企業には厳格な情報管理が求められています。プライバシーマークを取得することにより、顧客や取引先に対して信頼性の高い情報管理体制をアピールでき、結果的に企業価値の向上につながるのです。
また、プライバシーマークの運用は、従業員の意識改革や内部体制の強化にも寄与し、企業全体のガバナンス向上につながる重要な取り組みといえます。
プライバシーマークと個人情報保護法の関係
プライバシーマーク制度は個人情報保護法の内容をベースとしており、企業が法令を遵守していると第三者機関が認証する仕組みです。
個人情報保護法はすべての事業者に遵守が求められる法律ですが、プライバシーマークはそれを上回る基準で運用されています。そのため、認証取得企業は法令以上の体制を整備していると評価されます。
つまり、プライバシーマークの取得は法的義務を超えた自発的な取り組みであり、企業の社会的責任を果たす手段としても位置づけられているのです。
ISMSとの違い
ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)は、情報全般のセキュリティを対象とした国際標準規格に基づくマネジメントシステムです。一方、プライバシーマークは、主に個人情報の保護に特化した国内認証制度です。
ISMSでは、情報セキュリティにおける機密性・完全性・可用性の3つを中心に管理します。一方、プライバシーマークでは、個人情報の収集・利用・保管・提供・廃棄に関するルールの策定と、その運用状況が主な審査対象となります。
つまり、ISMSが情報セキュリティ全般をカバーするものであり、プライバシーマークは個人情報保護に焦点を当てた制度である点が大きな違いです。
プライバシーマーク取得のメリット

プライバシーマークの取得には、企業活動において多くのメリットがあります。ここでは、4つのメリットについて詳しく解説します。
- 信頼性向上
- リスク管理の強化
- 社内の意識向上
- コンプライアンス強化
これら4つのメリットについて、詳しく解説します。
信頼性向上
プライバシーマークを取得していると、顧客や取引先に対して企業が個人情報を適切に管理している証明になるのです。
情報漏えいなどが相次ぐ現代において、情報保護に積極的な姿勢を示すことで、企業の信頼性は大きく高まります。また、新規取引先の開拓や入札案件への参加時にも有利に働くケースが多く、競争力の強化にもつながります。
安心して取引できる企業として選ばれるための判断要素の一つが、プライバシーマークの存在です。
リスク管理の強化
プライバシーマークの取得には、リスクアセスメントの実施や内部ルールの策定・改善が求められます。
これにより、企業内部での個人情報の取り扱いに関するリスクを把握し、予防的な対策を講じられます。万が一情報漏えいが発生した場合でも、事前に対応手順を整備しておくことで、被害を最小限に抑えられるのです。
このように、プライバシーマークの取得と運用は、企業のリスクマネジメント能力を高める重要な手段となります。
社内の意識向上
プライバシーマーク取得に向けた取り組みでは、全従業員が個人情報保護に関する教育を受けなければなりません。
これにより、日常業務で個人情報を取り扱う際の意識が高まり、ルールに則った行動が習慣化しやすくなります。従業員一人ひとりの意識向上は、社内の情報管理体制の強化や企業全体の信頼性も増します。
また、定期的な教育や見直しを行うことで、継続的な改善活動が促進される点も大きなメリットです。
コンプライアンス強化
企業による法律や規制の遵守は社会的責任の一環であり、事業継続において不可欠です。
プライバシーマーク取得のプロセスでは、個人情報保護法をはじめとする関連法令を正しく理解し、それに基づいて体制を構築しなければなりません。これにより、コンプライアンス意識が社内に定着し、不適切な情報管理による法的リスクを回避しやすくなります。
さらに、第三者機関による審査を通じて管理体制の有効性が証明される点も、企業の社会的信頼性を高めます。
プライバシーマークの取得手順

プライバシーマークを取得するためには、以下のステップで審査を受ける必要があります。
- 個人情報保護マネジメントシステムの構築
- 個人情報保護マネジメントシステムの運用
- 申請書類の作成
- 文書審査・現地審査
- 改善の実施
スムーズに取得できるよう手順を確認し、プライバシーマーク取得までのおおまかな流れを把握しましょう。
個人情報保護マネジメントシステムの構築
プライバシーマークを取得するためには、JIS Q 15001に基づいた個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の構築が必要です。
個人情報の収集・利用・保存・提供・削除など、すべての工程におけるルールと手続きを文書化し、組織的に管理する仕組みを整えます。
具体的には、以下の手順が含まれます。
- 個人情報の特定
- 利用目的の明確化
- 取得方法の適正性
- 第三者提供の有無
- 苦情対応の手順
また、組織内の役割分担や責任者の任命を行い、マネジメント体制を確立させなければなりません。リスク評価や内部監査の計画もこの段階で策定します。
個人情報保護マネジメントシステムの運用
個人情報保護マネジメントシステムの構築後、実際に運用することが大切です。PDCAサイクルをまわして運用しましょう。具体的には、以下の方法で個人情報保護マネジメントシステムを運用します。
まず、Planの段階では社内体制を整備しルールを構築します。これには、個人情報保護方針の策定やリスク対策の検討、内部規定の整備などが必要です。
Doの段階では、構築したルールに沿った運用が求められます。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 個人情報の目的内利用
- リスク対策の実践
- 従業員への教育
Checkの段階では、個人情報の取り扱い状況確認が必要です。個人情報保護マネジメントシステムの運用を確認するため、内部監査の実施や代表者による見直しを行います。
Actの段階では、構築したルールの改善が求められます。不適合に対して是正措置を講じたり、継続的改善を行ったりしなければなりません。
申請書類の作成
プライバシーマークの申請にあたり、提出書類を作成します。必要書類として、主に以下のものが挙げられます。
- プライバシーマーク付与適格性審査申込書
- 個人情報保護体制
- 事業者概要
- 個人情報保護マネジメントシステム文書の一覧
- 教育実施サマリー
- 内部監査・マネジメントレビュー実施サマリー
- 確認事項
- 登記事項証明書
- リスク分析結果の写し
これらはすべて、個人情報保護マネジメントシステムが実際に構築・運用されていることを証明する書類です。形式だけでなく、実際に運用されているかどうかが問われます。
書類作成時には、過不足がないように用意しましょう。また、誤字脱字や記載ミスがあると再提出を求められる場合もあるため、慎重に準備する必要があります。
文書審査・現地審査
申請書類が受理されれば、文書審査と現地審査が行われます。
文書審査では、提出された書類の内容が個人情報保護マネジメントシステムの基準に適合しているかどうか確認します。文書審査で基準を満たさない部分が見つかった場合には、現地審査までに改善しなければなりません。
次に、審査員が企業を訪問する現地審査が実施されます。現地審査では、実際にシステムが適切に運用されているかを評価します。評価においては、個人情報保護マネジメントシステム文書で定めたルールが守られているかのチェックが行われるのです。
また、従業員へのヒアリングも行われ、システムの運用が社内全体に浸透しているか、個人情報の重要性を理解しているかが審査されます。
改善の実施
審査の結果、不備や是正が必要な点があれば指摘事項文書が送られてきます。企業はその内容に基づいて、改善を行わなければなりません。
改善計画を立て、実施した内容を文書化し、再提出する必要があります。改善には、ルールの改訂、教育の追加実施、記録の整備などが含まれます。指摘事項を的確に把握し、具体的で実効性のある対策を講じることが、プライバシーマークの認証取得につながるのです。
プライバシーマークの取得費用・取得期間

プライバシーマークは、申請してすぐに取得できるものではありません。取得には一定の費用と期間が必要です。
ここでは、プライバシーマークの取得費用と取得期間について解説します。企業規模や準備状況によって異なるため、費用や期間の目安として参考にしてください。
費用
取得にかかる費用には、審査料や更新費用、教育・研修費、コンサルタント費用などが含まれます。審査にかかる費用には、申請料・審査料・付与登録料があり、企業規模によって変動します。
| 新規 | 更新 | |
| 大規模 | 1,257,144円 | 942,858円 |
| 中規模 | 628,573円 | 471,430円 |
| 小規模 | 314,288円 | 230,478円 |
このほかにも、教育・研修費やコンサルタント費用がかかります。コンサルタント費用は30万円〜100万円程度かかるケースが一般的です。自社内で対応する場合はコンサルタント費用を抑えられますが、専門知識が必要なため、外部のサポートを受ける企業も多いといえます。
費用の内訳を事前に把握し、予算を確保しましょう。
期間
プライバシーマークを取得するには、個人情報保護マネジメントシステムを構築してから申請までに、3か月間の運用が必要です。その後、申請や審査を経て問題がなければ通常7か月から8か月程度でプライバシーマークを取得できます。
取得までの期間は、社内体制の整備状況や文書作成・運用実績の有無によっても異なるため、注意が必要です。
プライバシーマーク取得のポイント

プライバシーマークを確実に取得するためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、以下4つの重要なポイントを紹介します。
- トップマネジメントの関与
- 社内体制・文書の整備
- 従業員への教育と意識向上
- コンサルタントの活用
スムーズにプライバシーマークを取得できるよう、これらのポイントを確認しましょう。
トップマネジメントの関与
1つ目のポイントは、トップマネジメントの関与です。企業の代表や経営層が積極的にプライバシーマークの取得に関与することが重要です。
トップマネジメントがプロジェクトを主導し、組織全体に対してその重要性を周知することで、現場の理解と協力が得られやすくなります。また、リソースの確保や決裁が迅速に進むため、スムーズな体制構築と運用が可能になります。
社内体制・文書の整備
社内体制や文書の整備も、プライバシーマーク取得のポイントとなります。
個人情報保護マネジメントシステムを構築・運用するには、明確な責任体制と役割分担が必要です。また、規程やマニュアル、記録書類などの文書も整備し、誰が見てもわかりやすい状態にする必要があります。特に、文書の内容通りに適切に運用できているかが審査で重視されます。
従業員への教育と意識向上
プライバシーマーク取得において、従業員への教育と意識向上が欠かせません。
従業員全員が個人情報の重要性を理解し、正しく取り扱えるようになる必要があります。そのためには、継続的な教育が重要であり、研修資料・記録の整備や定期的な見直しが求められます。
教育を通じて従業員の意識が高まれば現場での情報管理も徹底されやすく、個人情報保護マネジメントシステムのスムーズな運用につながるのです。
コンサルタントの活用
自社内にノウハウがない場合、コンサルタントの活用が、取得への最も確実な近道です。
プライバシーマークの取得プロセスは複雑で、JIS規格、法律、審査基準への深い理解が求められます。担当者が本来の業務と兼任しながら、膨大な文書作成や審査対応を行うのは、多大な負担となり、プロジェクトが頓挫する原因にもなりかねません。
経験豊富なコンサルタントは、最新の審査傾向を踏まえ、体制構築から文書作成、審査対応までをワンストップでサポートします。結果として、担当者の負担を大幅に軽減し、より早く、より確実な認証取得が可能となります。
プライバシーマーク取得には準備が必要

プライバシーマークの取得は企業の信頼性を飛躍的に高める一方、そのプロセスは複雑で、多くの時間と専門知識を要します。
「何から手をつければいいか分からない」
「担当者のリソースが足りない」
「審査に落ちるリスクが不安だ」
もし、このような課題をお持ちでしたら、コンサルタントの力を借りることを強くお勧めします。
日本パープルが提供する「Coach Mamoru(コーチマモル)」は、情報セキュリティ分野に精通したコンサルタントが、貴社のプライバシーマーク取得・更新を徹底的にサポートします。20,000社を超える事業所との取引実績を持ち、お客様の実態・ご要望に合わせた「オーダーメイド型」支援で、確実な認証取得へ導きます。
プライバシーマークの取得・更新に関してお困りの際は、お気軽にご相談ください。