リモートワーク時代の情報セキュリティ対策を解説!リスクや事例も紹介

近年、リモートワークが広まっています。それに伴い、情報セキュリティリスクも変化しており、リモートワーク時代に合わせたセキュリティ対策が必要です。
本記事では、リモートワーク時代の情報セキュリティリスクやその対策について解説します。併せて、情報セキュリティが十分でなかった際の事故事例も紹介します。
リモートワークを実施している企業やテレワーク導入を検討している企業の担当者は必見です。
リモートワーク時代の情報セキュリティリスク
リモートワーク時代のセキュリティ事故事例
リモートワーク時代の情報セキュリティ対策
ISMSやプライバシーマークを取得・維持するメリット
リモートワーク時代に合わせた情報セキュリティ対策を
リモートワーク時代の情報セキュリティリスク

リモートワークの普及により働く場所や時間に柔軟性が生まれた一方で、情報セキュリティに関する新たなリスクも発生しています。従来のオフィス環境であれば管理が行き届いていたセキュリティも、社外業務の増加に伴いさまざまな脅威にさらされる可能性が高まっているのです。
そこで、リモートワーク特有の情報セキュリティリスクを解説します。
情報漏えいのリスク
社外での業務中に、機密情報や個人情報などが第三者に漏えいする可能性があります。例えば、自宅での作業中に家族が画面をのぞき見てしまったり、公共の場所での作業中に画面が外部から見えてしまったりするケースが考えられます。
また、誤ってファイルを他者に送信してしまうなど、ヒューマンエラーによる情報漏えいも少なくありません。情報漏えいは企業の信用を大きく損なうリスクとなるため、注意が必要です。
マルウェアへの感染リスク
業務に使用するデバイスがウイルス対策されていない場合、マルウェアやスパイウェアなどに感染する危険性が高まります。
特に、同じデバイスで業務作業とプライベート利用を行っていると、信頼できないウェブサイトの閲覧や、不信なメールの添付ファイル開封が原因で感染するケースがあります。感染したデバイスを通じて社内ネットワークへ被害が拡大する場合もあるため、社外で使うデバイスでもマルウェアへの十分な対策が必要です。
デバイスの紛失や盗難によるリスク
ノートパソコンやスマートフォンなど、業務に使用するモバイルデバイスの紛失や盗難も、リモートワークならではのリスクとして挙げられます。データが入ったUSBメモリを紛失したり、社外で作業をしていて席を離れた際にデバイスの盗難に遭ったりする可能性が高いのです。
たとえパスワードやロックがかかっていても、デバイス内部のデータを抜き取られる可能性はゼロではありません。特に、デバイスに業務用の機密データが保存されていた場合、その漏えいリスクは甚大です。
不正アクセスのリスク
リモート環境では、セキュリティの脆弱性を狙って正規の社員になりすまし接続を試みる、不正アクセスのリスクも高まります。
例えば、プライベートと同じパスワードの使い回しや簡単なパスワード設定により、外部からシステムへ侵入されるケースがあります。これにより、内部の情報や顧客データが盗まれる危険性があるため、リモート環境においても強固な認証体制が求められるのです。
私物デバイスの使用リスク
BYOD(Bring Your Own Device)と呼ばれる私物デバイスの業務利用もリスクの一因です。私物のスマートフォンやパソコンは企業のセキュリティ基準を満たしていないケースが多く、脆弱性に対応する対策がなされていない可能性があります。
また、業務に使用しないアプリのインストールや家族との共有によって、業務情報が意図せず漏えいするリスクも高まります。そのため、私物デバイスを業務に使用する際は、セキュリティソフトの導入や定期的な更新が不可欠です。
安全ではないネットワーク利用のリスク
カフェや空港など、公共Wi-Fiを利用した業務は、通信内容が盗み見られるリスクがあります。これらのネットワークは暗号化が不十分であるケースが多く、Man-in-the-Middle攻撃と呼ばれる悪意のある第三者による中間者攻撃などが発生しやすい環境です。
安全な通信手段を確保しないまま業務を行うことは、情報漏えいのリスクを高めます。そのため、リモートワークの際にはデバイスのみならず、使用するネットワークの安全性も確認する必要があるのです。
リモートワーク時代のセキュリティ事故事例

働き方に変化が生まれるなかで、実際にリモートワークを狙ったセキュリティ事故が発生しています。ここでは、リモートワーク時代のさまざまなセキュリティ事故事例を原因別に5つの事例を解説しているので、参考にしてください。
ウイルス感染
リモートワークの際にウイルスへ感染してしまい、情報が漏えいしてしまった事例があります。
原因は、リモートワーク中に社内ネットワークを使用せず、社用パソコンでSNSに接続し、第三者から送られたファイルをダウンロードしたことです。その結果、社用パソコンがウイルスに感染しました。さらに、そのまま社内ネットワークに接続したため、社内の別のパソコンにもウイルスが広まってしまったのです。
これにより、従業員の個人情報やサーバーのログなどが流出し、企業の信頼が著しく低下しました。
VPNの脆弱性を悪用した不正アクセスと情報漏えい
VPNとは、インターネット上に仮想的な専用線を作り、データを安全に送受信する仕組みを指します。VPNによって社外のパソコンと会社をつなぐことで、リモートワークでも安全にデータのやり取りを行えるようになります。
しかし、VPNの使用には注意が必要です。なぜなら、VPNパスワードが流出すると、誰でもアクセスできるようになってしまうからです。
実際、VPN機器のアップデートを怠ったためその脆弱性を悪用され、不正アクセスの被害に遭うケースが急増しており、VPN機器を利用する際には適切なセキュリティアップデートが非常に重要です。
デバイス紛失
リモートワークを行うために社外へ持ち出したデバイスを紛失したり盗難に遭ったりして、情報が流出する場合もあります。
例えば、リモートワークのために個人情報が入ったUSBメモリを持ち出したものの、不注意によって紛失してしまったケースが挙げられます。それ以外にも、ワークスペースなどで作業中トイレへ行くために席を離れたスキを突き、デバイスが盗難される可能性もあるのです。
パスワード流出
リモートワークに使用していた社用のデバイスに偽のメールが届き、IDやパスワードを入力してしまった事例もあります。これにより、アカウントの情報が漏えいし、不正アクセスの被害に遭い、個人情報が流出してしまったのです。
このように、悪意を持った不正メールを開いてしまうケースは少なくありません。しかし、従業員に不審なメールを見分ける力があれば、被害を避けられます。そのため、従業員への情報セキュリティ教育が非常に重要です。
内部不正による情報持ち出し
従業員や元従業員の内部不正によって、情報が持ち出されるケースもあります。
実際に、ネットワークセキュリティの製品を取り扱っている会社でも、元従業員が情報を持ち出すケースがありました。持ち出された情報は第三者により、詐欺犯罪に使用されていたようです。
そのため、従業員のみならず退職者に対してもアクセス制限や機密情報の保持を禁止するなどの対策が必要です。
リモートワーク時代の情報セキュリティ対策
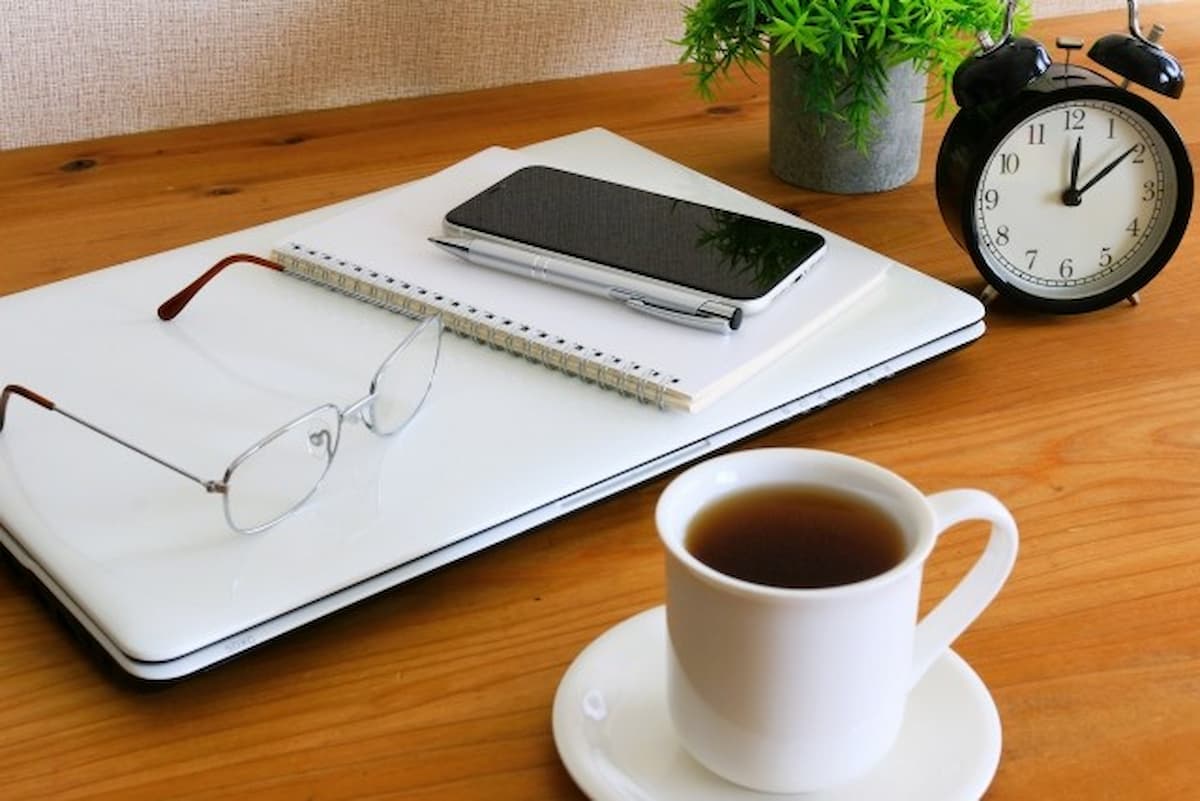
リモートワーク時代において企業が情報資産を守るためには、従来のセキュリティ対策だけでなく、新たな働き方に対応した施策が必要です。ここでは、リモートワークにおける具体的な情報セキュリティ対策を紹介します。
いずれか一つを行えばよいわけではなく、複数の対策を組み合わせて網羅的に実施することが重要です。
セキュリティポリシー/社内ガイドラインの策定
まず基本となるのが、セキュリティポリシーや社内ガイドラインの策定です。リモートワーク特有のリスクに対応するために、どのような行動やルールが求められるのかを明文化し、従業員全体に共有することが重要です。これにより、従業員がリスクを避ける意識を持ちやすくなります。
また、情報セキュリティリスクは常に変化するため、セキュリティポリシーや社内ガイドラインの定期的な見直しや周知徹底も必要です。
アクセス権限の最小化
情報資産に対するアクセス権限は、業務に必要な範囲に限定するのが原則です。アクセス権限の付与を最小限に抑え、情報資産を閲覧できるユーザーを減らすことで、情報漏えいのリスクを減らします。
過剰にアクセス権限を持たせると、万が一アカウントが乗っ取られた場合の被害が拡大する可能性が高まります。部署や役職ごとに権限を見直し、最小限の範囲で業務が完結するよう管理することが、セキュリティの強化につながるのです。
VPNの導入
安全な通信経路を確保するためには、VPNと呼ばれる仮想プライベートネットワークの導入が有効です。VPNを利用すれば、外部からのアクセスも暗号化されるため、第三者による盗聴や不正アクセスのリスクを大幅に減らせます。
特に、リモートワーク時に公共Wi-Fiを使用する際、安全ではないネットワークに接続しなければならないケースもあります。しかし、VPNを導入すればデータの送受信を暗号化できるため、ネットワークの安全性が確保できていない状況では必須の対策と言えるでしょう。
多要素認証の導入
情報セキュリティリスクの高まりにより、データへのアクセスを認証する際、パスワードだけでは不十分な時代となっています。
そのため、ログイン時の多要素認証を導入することが重要です。パスワードに加えてワンタイムパスワードや生体認証などを組み合わせ、不正アクセスを防止します。
たとえパスワードが流出しても、他の要素がなければログインできないため、より安全性を高められるのです。
ソフトウェアの更新
業務用のデバイスやアプリケーションは、常に最新の状態に保たなければなりません。もちろん、私物デバイスを使用する際には私物デバイスのソフトウェアも更新する必要があります。
古いバージョンにはセキュリティホールが存在する可能性があり、マルウェアやウイルスに感染するリスクが高くなります。自動更新を有効にする、定期的に更新状況を確認するなど、ソフトウェアを最新の状態に更新し続けましょう。
資産管理ツールの導入
企業が従業員の使用するデバイスやソフトウェアを一元管理するために、資産管理ツールの導入が有効です。
これにより、どのデバイスでどのバージョンのソフトウェアを使用しているかを把握しやすくなり、リスクの高いソフトウェアなどを早期に発見できます。また、資産管理ツールを導入すれば、使用しているデバイスのセキュリティアップデートも一斉に実施でき、デバイスを最新の状態に保てます。
加えて、不正なソフトウェアの使用やデバイスの無断利用を抑制できるのです。
危険なソフトウェアへの対策
業務に不要なソフトウェアや出所不明なアプリケーションの使用は、情報セキュリティリスクを高めます。これらの危険なソフトウェアをダウンロードすると、ウイルスなどに感染するおそれがあります。そのため、ホワイトリスト形式で許可されたソフトウェア以外の使用を制限する、ダウンロード制限を設けるなどの対策を講じましょう。
また、従業員が危険なソフトウェアをダウンロードしないよう注意喚起を行い、意識を高めることも重要です。
デバイス管理の徹底
リモートワーク環境では、従業員が使用するデバイスの管理が鍵となります。セキュリティソフトの導入や、紛失・盗難時にデータを遠隔で削除できるMDMと呼ばれるモバイルデバイス管理ツールの活用などにより、デバイスレベルでの情報漏えい防止対策を行わなければなりません。
また、定期的なデバイスチェックや利用ルールの整備も効果的です。
従業員へのセキュリティ教育
どれだけシステム面で対策をしても、最終的には従業員のリテラシーがセキュリティを左右します。実際にデバイスや情報を扱うのは従業員であり、現場での適切な判断が求められるのです。
フィッシングメールの見分け方や、パスワード管理の重要性など、基礎的な知識を継続的に教育・研修する必要があります。また、定期的な訓練やテストの実施もセキュリティ教育として効果的です。
ISMSやプライバシーマークを取得・維持するメリット

リモートワークが進むなかで、外部の認証制度を取得・維持することは企業の信頼性を高める有効な手段です。特に、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)やプライバシーマークの取得は、対外的な信頼の証明となり取引先や顧客への安心材料にもなります。
そこで、ISMSやプライバシーマークの取得・維持のメリットをそれぞれ解説します。
ISMS取得・維持のメリット
ISMSとは、情報セキュリティを組織的に管理・運用することです。ISMSを構築し、国際規格を満たせば、ISMS認証を取得・維持できます。これにより、社内に明確なセキュリティ方針が根付き、情報の取扱いやリスク管理が体系化されます。
また、外部監査を通じて継続的な改善が求められるため、セキュリティレベルの維持・向上にもつながるのです。そのため、ISMS認証を取得・維持すれば対外的にセキュリティレベルの高さをアピールでき、顧客や取引先からも信頼を得られます。
ISMSについては「ISO27001(ISMS)とは?その概要と取得に向けた流れを解説」の記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
プライバシーマーク取得・維持のメリット
プライバシーマークは、個人情報を適切に取り扱っている旨を第三者が認定する制度です。
プライバシーマークは、日本産業規格の基準を満たして個人情報を扱っている企業に付与されます。そのため、プライバシーマークを取得・維持すれば、企業は個人情報保護の意識が高いと対外的にアピールできるのです。特に、個人情報を多く扱う業種では信頼の獲得につながります。
また、従業員の情報管理意識も向上し、社内のセキュリティ文化を定着させるためにも効果を発揮するのです。
プライバシーマークについては「プライバシーマークとは?取得するメリットを解説」の記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
リモートワーク時代に合わせた情報セキュリティ対策を

リモートワークが普及するにつれ、それに合わせた情報セキュリティ対策が求められています。特に、ISMSやプライバシーマークの取得・維持は対外的にもセキュリティの高さをアピールできるのです。
日本パープルが提供するCoach Mamoru(コーチマモル)は、情報セキュリティ分野に精通した講師が、ISMS認証やプライバシーマークの取得・維持をサポートします。7,000社以上の取引実績を持ち、お客様の実態やご要望に合わせた「オーダーメイド型」支援を提供しています。
ISMS認証やプライバシーマークの取得や維持にお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。





















